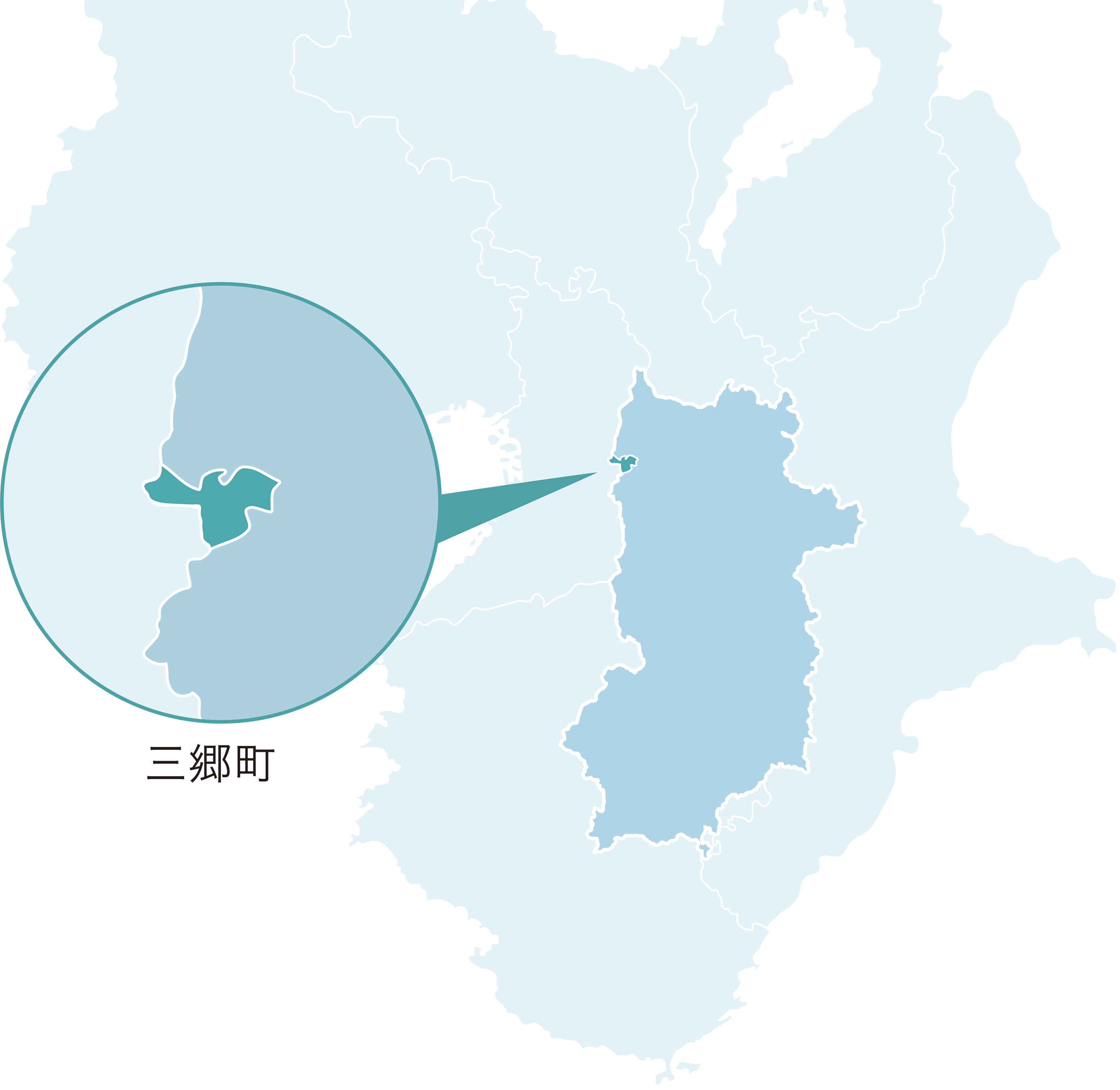本文
後期高齢者医療保険 制度について
平成20年4月から、75歳以上(ただし一定の障がいのある方は65歳以上75歳未満の方で、申請により認定を受けた方)の方は、すべて後期高齢者医療制度による医療を受けることになりました。後期高齢者医療制度は、すべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が主体となり、市町村と事務を分担して運営しています。
一定の障がいとは・・・
- 障害基礎年金の1級または2級に該当する方
- 身体障害者手帳の1級から3級と4級の一部(下肢障害の1号、3号または4号及び音声言語機能の障害)に該当する方
- 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級に該当する方
- 療育手帳Aに該当する方
制度について、詳しくは奈良県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>をご覧ください。
後期高齢者医療広域連合と市町村の事務分担
|
後期高齢者医療広域連合が行うこと |
市町村が行うこと |
|---|---|
|
資格の管理 |
資格確認書・資格情報のお知らせの引渡し |
|
保険料の算定、賦課 |
保険料を集める |
|
医療給付 など |
申請、届出の受付など |
資格確認書
※マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降、保険証の新たな発行はなくなりました。マイナ保険証の利用が原則となります。
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを保険証として利用登録をしていない方等
については、資格確認書を交付予定です。(令和7年7月中旬ごろ予定)
※現在お持ちの保険証は、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
負担割合について
世帯の被保険者のうち、最も所得が高い方の市町村民税課税所得によって決まります。
| 市町村民税の課税所得 | 一部負担割合 |
|---|---|
|
28万円未満 |
1割 |
|
28万円以上145万円未満※ |
2割 |
|
145万円以上 |
3割 |
(診療月が4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当年度の市町村民税課税所得)
*保険適用外診療は、全額自己負担になります。
※市町村民税課税所得が28万円以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以下の方は1割となります。(同一世帯に被保険者が2人以上の場合は320万円以下)
【基準収入額適用申請】
・市町村民税課税所得が145万円以上の方でも世帯の被保険者(後期高齢者医療保険加入者)の収入合計が520万円未満(一人の場合は383万円未満)の場合、基準収入額適用申請をすると一部負担金が1割または2割に変更されます。
・市町村民税課税所得が145万円以上の方で、被保険者一人で383万円以上でも、世帯で70歳以上の方を含めて収入合計が520万円未満の場合、基準収入額適用申請をすると一部負担金が1割または2割に変更されます。
[申請に必要なもの]
- 保険証または資格確認書
- 収入を確認できる書類(確定申告書等)
※基準収入額適用申請による負担割合の変更は、申請日の翌月1日からの適用となります。
医療機関での自己負担限度額について
医療機関等で支払った一部負担金が下記の限度額を超えた場合に、超えた金額が高額療養費として支給されます。なお、外来・入院いずれの場合も、1カ月間の同一医療機関での負担は自己負担限度額までの支払いにとどめられます。また、低所得者の取扱いを受けるには、限度額適用・標準負担額減額認定証または資格確認書が必要です。(マイナ保険証利用の方は不要です。)
※但し、食事療養標準負担額や差額ベット代等の保険外費用は対象外です。
1割・2割負担
| 所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | 食事療養標準負担額 (1食あたり) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般Ⅱ(2割) |
18,000円または【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】の低い方を適用(令和7年9月まで) (年間の上限144,000円) |
57,600円 |
510円 |
|||
| 一般Ⅰ(1割) |
18,000円 |
|||||
| 低所得者Ⅱ(1割) | 8,000円 | 24,600円 |
240円【注2】 |
|||
|
低所得者I(1割) |
8,000円 | 15,000円 |
110円 |
|||
※非課税世帯の人は、低所得者Ⅰまたは低所得者Ⅱに該当します。「限度額適用・標準負担額減額認定証」、もしくは資格確認書を医療機関の窓口に提示すると、窓口でのお支払が自己負担限度額までになります。お持ちでない場合は、保険課窓口にて申請が必要です。(マイナ保険証利用の方は不要です。)
(申請に必要なもの)
- 本人確認できるもの
- 申請者の本人確認できるもの(本人に代わり申請される場合)
- 保険証
- 委任状(別住所の方が本人に代わり申請される場合)
【注1】過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目以降は「多数回」該当となり上限額が下がります。
【注2】低所得者Ⅱで申請月から過去1年間(認定期間中)に90日以上入院している場合は91日目から190円。改めて役場にて申請が必要です。
- 入院日数が90日以上であることがわかる書類(領収書等)
- 保険証と限度額適用・標準負担額減額認定証、または資格確認書
3割負担
| 所得区分 | 外来+入院(世帯ごと) | 食事療養標準負担額 (1食あたり) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得Ⅲ 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈多数回141,000円〉 |
510円 |
|||
| 現役並み所得Ⅱ 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈多数回93,000円〉 |
||||
| 現役並み所得I 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈多数回44,400円〉 |
||||
(*)過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目以降は「多数回」該当となり上限額が下がります。
現役並み所得I、Ⅱの方は、あらかじめ「限度額適用認定証」、もしくは資格確認書を医療機関の窓口に提示すると、窓口でのお支払が自己負担限度額までになります。お持ちでない場合は、保険課窓口にて申請が必要です。(マイナ保険証利用の方は不要です。)
(申請に必要なもの)
- 本人確認できるもの
- 申請者の本人確認できるもの(本人に代わり申請される場合)
- 保険証
- 委任状(別住所の方が本人に代わり申請される場合)
下記ホームページもご覧ください。
奈良県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)<外部リンク>