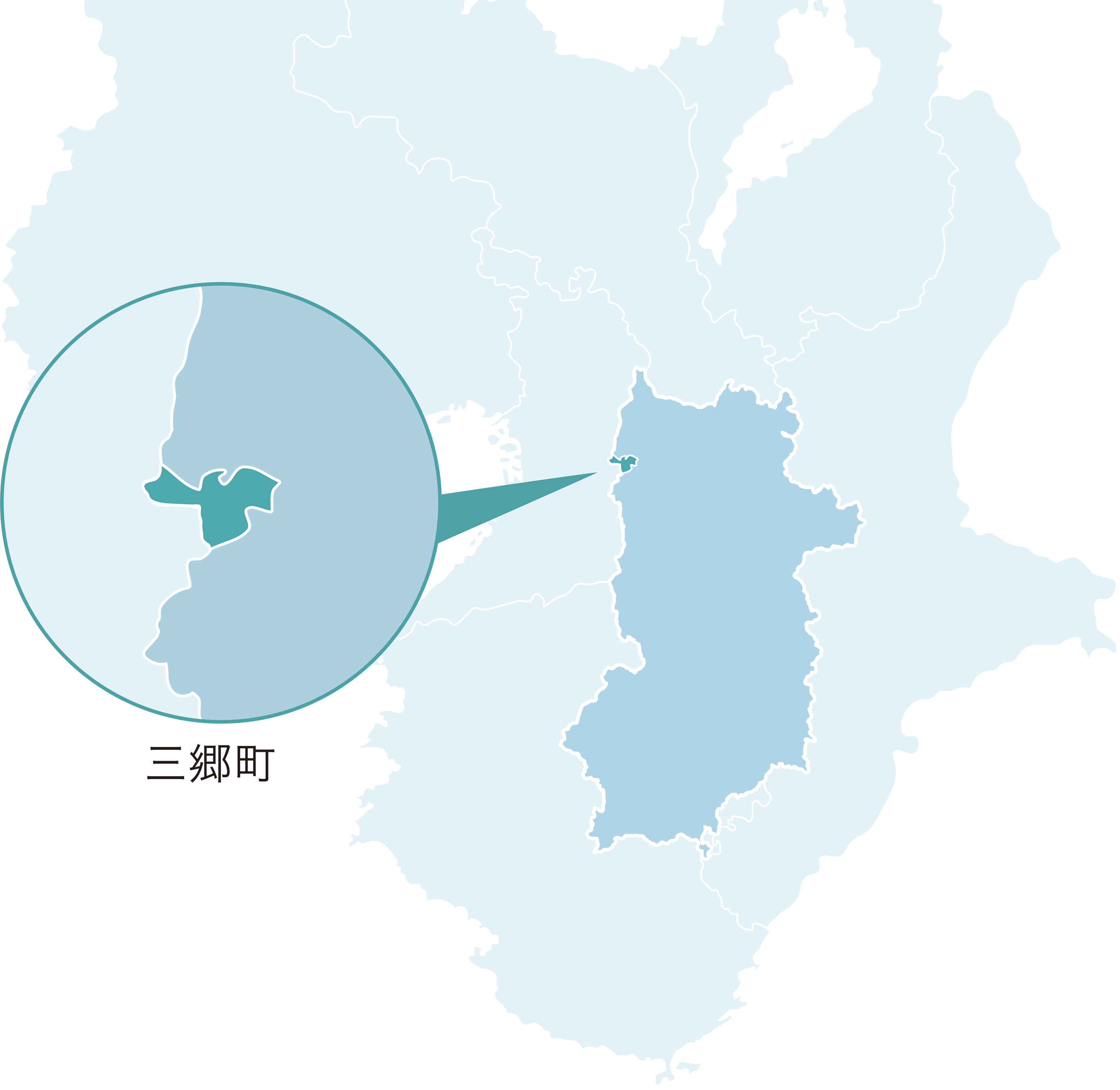本文
子どもの予防接種
予防接種を受けましょう
お母さんから赤ちゃんが生まれた時にプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、成長するとともに自然に失われていきます。そのため、赤ちゃんは自分自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが、予防接種です。
予防接種には予防接種法によって、対象疾病、対象者および接種期間などが定められた、定期接種と、それ以外の任意接種があります。予防接種には病気ごとにそれぞれ接種に適した時期があります。標準的な接種時期に受けましょう。
事前に、母子手帳発行時に配布した「予防接種と子どもの健康」の冊子をよく読み、予防接種の効果や副反応などについて理解しましょう。体調など、心配なことはかかりつけ医によく相談し、納得した上で接種してください。
転入などで予診票が手元に無い方は、接種対象の方の母子健康手帳を持って、すこやか健康課までお越しください。
予防接種の計画を立てましょう
予防接種の具体的な順序や日程は、お子さんの体調などをみて、かかりつけ医と相談して決めてください。
予防接種の種類と接種間隔
予防接種の種類
- 注射生ワクチン(BCG・麻しん風しん混合ワクチン・水ぼうそう・おたふくかぜ)
- 経口生ワクチン(ロタウイルスワクチン)
- 不活化ワクチン(B型肝炎ワクチン、ヒブ、小児肺炎球菌、5種混合、4種混合、日本脳炎、インフルエンザ、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン)
接種間隔
- 注射生ワクチンの次に注射生ワクチンを接種する場合、27日以上の間隔をあけます。
- それ以外のワクチンの組み合わせでは接種間隔の制限はありません。
- ただし、小児肺炎球菌やヒブワクチンなど同一ワクチンを複数回接種する必要があるものは、それぞれ定められた間隔で接種してください。
定期の予防接種
- ロタウイルスワクチン(令和2年8月1日以降に出生したお子さんが定期接種対象となります。7月31日以前に出生したお子さんは任意接種となりますのでご注意ください。詳細はロタウイルスワクチンのページをご覧ください。)
- BCG
- B型肝炎ワクチン
- 5種混合(DPT-IPV-Hib):ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ
- 4種混合(DPT-IPV):ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ
- 2種混合(DT):ジフテリア・破傷風
- 麻しん・風しん(MR)
- 日本脳炎
- ヒブワクチン
- 小児肺炎球菌ワクチン
- 水痘ワクチン
- ヒトパピローマウイルスワクチン
定期の予防接種には、自己負担はありません。
予防接種法に基づく定期予防接種スケジュールは、以下のようになっています。
ロタウイルスワクチン
- ロタリックス
対象者:出生6週0日後から24週0日後まで
(初回接種の標準的な接種期間は生後2か月から出生14週6日まで)
接種回数:27日以上の間隔をあけて2回接種 - ロタテック
対象者:出生6週0日後から32週0日後まで
(初回接種の標準的な接種期間は生後2か月から出生14週6日まで)
接種回数:27日以上の間隔をあけて3回接種
ロタウイルスワクチンは、ロタリックスとロタテックの2種類があります。
BCG
対象者:生後1歳に至るまでの間にある者(標準的な接種期間は生後5か月に達した時から生後8か月に達するまで)1回
B型肝炎ワクチン
対象者:生後1歳に至るまでの間にある者(標準的な接種期間は生後2か月に至った時から生後9か月に至るまで)
初回:27日以上の間隔で2回
追加:1回目接種から139日以上あけて1回
5種混合(DPT-IPV-Hib):ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ
対象者:生後2か月から生後90か月に至るまでの間にある者 ※令和6年4月1日から定期接種になりました。
1期初回接種:20日から56日までの間隔をおいて3回
(標準的な接種期間は生後2か月に達した時から生後7か月に達するまで)
1期追加接種:初回接種(3回)終了後6か月以上の間隔をおいて1回
(標準的な接種期間は初回接種(3回)終了後、6か月から18か月までの間隔をおいて1回)
4種混合(DPT-IPV):ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ
対象者:生後2か月から生後90か月に至るまでの間にある者 ※原則、令和6年3月31日までに1回でも受けたことのある方に限ります。
1期初回接種:20日から56日までの間隔をおいて3回
(標準的な接種期間は生後2か月に達した時から生後12か月に達するまで)
1期追加接種:初回接種(3回)終了後6か月以上の間隔をおいて1回
(標準的な接種期間は1期初回終了後、12か月に達した時から18か月に達するまで)
2種混合(DT):ジフテリア・破傷風
対象者:11歳以上13歳未満の者
1回
- 予診票と説明書は、対象の方に年度初めに送付します。
麻しん・風しん
対象者:
1期:生後12か月から生後24か月に至るまでの間にある者 1回
2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学前の1年の間にあるもの(いわゆる年長児)1回
- 2期の対象の方には、年度初めに予診票と説明書を送付します。
日本脳炎
対象者:
1期:生後6か月から生後90か月に至るまでの間にある者
- 初回接種:6日から28日までの間隔をおいて2回(標準的な接種期間は3歳に達した時から4歳に達するまで)
- 追加接種:1期初回(2回)終了後、6か月以上(標準的にはおおむね1年)おいて1回(標準的な接種期間は4歳に達した時から5歳に達するまで)
2期:9歳以上13歳未満の者 1回
(標準的な接種期間は9歳に達した時から10歳に達するまで)
- 平成19年4月1日以前に生まれた方は20歳の誕生日の前日まで接種可能です。詳細は日本脳炎のページをご覧ください。
- 2期の対象の方には、年度初めに予診票と説明書を送付します。
ヒブワクチン
対象者:生後2か月から生後60か月に至るまでの間にある者 ※原則、令和6年3月31日までに1回でも受けたことのある方に限ります。
接種回数は、ワクチンを初めて接種する年齢によって異なります。かかりつけ医に相談して、スケジュールを決めましょう。
標準的な接種スケジュールで接種した場合
| 接種開始年齢 | 接種回数 | 接種方法 |
|---|---|---|
|
生後2か月以上 |
4回 |
1回目接種→(27日~56日の間隔)→2回目接種 |
標準的なスケジュールで接種しなかった場合
接種開始の年齢によりスケジュールが異なります。
|
接種開始年齢 |
接種回数 |
接種方法 |
|---|---|---|
|
生後7か月以上 |
3回 |
1回目接種→(27日~56日の間隔)→2回目接種 |
|
1歳以上5歳未満 |
1回 |
1回接種で終了 |
小児肺炎球菌ワクチン
対象者:生後2か月から生後60か月に至るまでの間にある者
接種回数は、ワクチンを初めて接種する年齢によって異なります。かかりつけ医に相談して、スケジュールを決めましょう。
標準的な接種スケジュールで接種した場合
| 接種開始年齢 | 接種回数 | 接種方法 |
|---|---|---|
|
生後2か月以上 |
4回 |
1回目接種→(27日以上の間隔)→2回目接種 |
標準的なスケジュールで接種しなかった場合
接種開始の年齢によりスケジュールが異なります。
| 接種開始年齢 | 接種回数 | 接種方法 |
|---|---|---|
|
生後7か月以上 |
3回 |
1回目接種→(27日以上の間隔)→2回目接種(生後2歳未満) |
|
12か月以上 |
2回 |
1回目接種→(60日以上の間隔)→2回目接種 |
|
24か月以上5歳未満 |
1回 |
1回接種で終了 |
水痘ワクチン
対象者:生後12か月から生後36か月に至るまでの間にある者
3か月以上(標準的には6か月~12か月未満)の間隔をおいて2回
ヒトパピローマウイルスワクチン
対象者:小学校6年生~高校1年相当の女子
令和5年4月1日から、2価ワクチンと4価ワクチンに加え、9価ワクチンが受けられるようになっています。
かかりつけの医師とよく相談してどのワクチンを接種するか選びましょう。
標準的な接種スケジュール
| 種類 | 接種間隔 |
|---|---|
|
2価ワクチン |
1回目接種→2回目(1回目接種から1か月後)→3回目(1回目接種から6か月後) |
|
4価ワクチン |
1回目接種→2回目(1回目接種から2か月後)→3回目(1回目接種から6か月後) |
| 9価ワクチン |
〇15歳の誕生日の前日(15歳未満)までに1回目の接種を受ける方 2回接種:1回目接種→2回目(1回目の接種から6か月後※) ※ただし、2回目接種が1回目接種から5か月未満であった場合は、3回目接種が必要。 3回目接種は、2回目接種から3か月以上の間隔をあけて接種。
〇15歳になってから1回目の接種を受ける方 3回接種:1回目接種→2回目(1回目接種から2か月後)→3回目(1回目接種から6か月後)※上記の方法で接種できない場合は、1ヶ月以上の間隔をあけて2回目接種。 かつ2回目の接種から3か月以上あけて3回目接種。 |
任意の予防接種
任意の予防接種とは、おたふくかぜ・インフルエンザなどです。
令和2年7月31日以前に出生したお子さんがロタウイルスワクチンを
接種した場合、町からの一部助成があります。
詳細はロタウイルスワクチンのページをご覧ください。