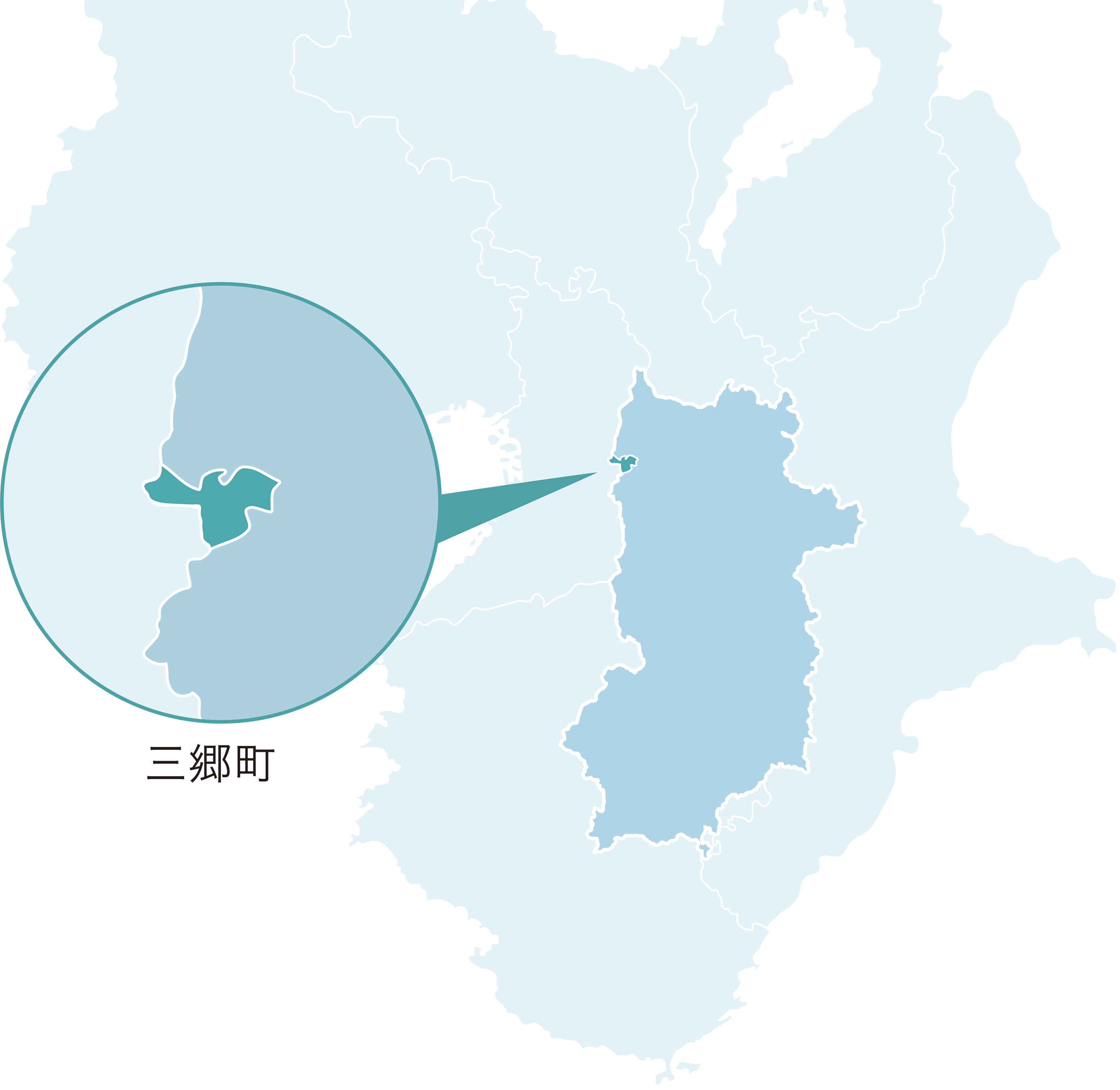本文
令和7年度 国民健康保険税
令和7年度の国民健康保険税について
国民健康保険税の税率
令和7年度の奈良県内統一保険税率は、下表のとおりです。
|
|
医療給付費分 (病気やケガをしたときの医療費の財源となる保険税) |
後期高齢者支援金等分 (後期高齢者医療制度を支えるための財源となる保険税)
|
介護納付金分(40~64歳の方のみ) (介護保険制度を支えるための財源となる保険税)
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
令和6年度 |
令和7年度 |
令和6年度 |
令和7年度 |
令和6年度 |
令和7年度 |
|
|
所得割 |
7.64% |
7.64% (増減なし) |
3.27% |
3.27% (増減なし) |
3.03% |
3.03% (増減なし) |
|
均等割 |
27,600円 |
27,600円 (増減なし) |
11,500円 |
11,500円 (増減なし) |
16,900円 |
16,900円 (増減なし) |
|
平等割 |
20,000円 |
20,000円 (増減なし) |
8,400円 |
8,400円 (増減なし) |
― |
― |
所得割・・・前年の総所得金額等(基礎控除後)の合計額に応じて計算
均等割・・・加入者1人当たりの金額
平等割・・・1世帯当たりの金額
保険税の算定方法
世帯の年間保険税額は、医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分でそれぞれ次の計算方法で算定し、その合計を国民健康保険税として納めます。
世帯の年間保険税額=医療給付費分+後期高齢者支援金等分+介護納付金分
- 医療給付費分=平等割額+均等割額+所得割額
- 後期高齢者支援金等分=平等割額+均等割額+所得割額
- 介護納付金分=均等割額+所得割額
※ただし、課税限度額は以下のとおりです。
- 医療給付費分 650,000円
- 後期高齢者支援金等分 240,000円
- 介護納付金分 170,000円
所得が少ない世帯に対する軽減について
所得の少ない世帯に対して、前年中の世帯所得合計額が以下の基準に該当する場合、均等割と平等割について、軽減割合に応じ減額し算定します。ただし、所得の少ない世帯でも所得申告がされていない場合は、軽減の対象になりません。
| 軽減割合 |
世帯主(擬制世帯主含む)及びその世帯に属する被保険者全員の前年中の「総所得金額等の合計額」が次の金額以下の世帯 ※(給与所得者等の数-1)は給与所得等の数が2人以上の場合に適用 |
|---|---|
| 7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 5割 | 43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 2割 | 43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
※給与所得者等の数とは、一定額(55万円)を超える給与収入を有する人または一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は125万円)を超える公的年金の受給を受ける方のことです。
※被保険者数とは、国民健康保険に加入している方および国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、継続して同一の世帯に属する方の数をいいます。
軽減割合を算定するときは、次のことに注意してください
- 65歳以上の公的年金受給者は、年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。
- 事業所得については、専従者控除を差し引く前の金額で判定。(専従者本人の給与とは扱わない。)
- 土地・家屋などの譲渡所得については、特別控除前の所得です。
その他軽減等について
世帯内に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行される方がおられることによる国民健康保険税の軽減措置について(旧国保)
後期高齢者医療制度に国保から直接移行する方がいる世帯では、同じ世帯に属する方の国保税について、次のような措置を行います。ただし、措置期間中に世帯構成が変わるなどすると対象外となる場合があります。
手続きは必要ありません。
- 軽減判定について
国保税の軽減判定(7割・5割・2割)を、世帯内の後期高齢者医療制度に移行した方の所得と人数を含めて行います。 - 国民健康保険の被保険者が1人となる場合
最初の5年間は平等割(介護分除く)が2分の1軽減となり、(5年経過後も同じ状況が続く場合)その後の3年間は4分の1軽減となります。
社会保険から後期高齢者医療制度に直接移行する方の被扶養者に対する減免(旧被扶養者)
社会保険(被用者保険)から後期高齢者医療制度に直接移行する方の被扶養者であった65歳以上の方(旧被扶養者)が、新たに国保に加入する場合、申請いただくことで、減免を受けていただくことができます。
すでに令和6年度以前より適用を受けている方は、改めての届出は必要ありません。
詳細については、旧被扶養者に係る保険税の減免をご確認ください。
非自発的失業者国民健康保険税の軽減措置
倒産や解雇など自ら望まない形により離職した失業時65歳未満の方(非自発的離職者)は、退職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの国民健康保険税を算定する際に前年の給与所得を100分の30として計算します。
ハローワークで発行される雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11、12、21、22、31、32、23、33、34」のいずれかであることが条件となります。雇用保険受給資格者証等をお持ちでない場合は適用できません。
すでに令和6年度より適用を受けている方は、改めての届出は必要ありません。
詳細については、非自発的失業者国民健康保険税の軽減措置をご確認ください。
未就学児の均等割額の2分の1を軽減します
子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)に係る均等割額の2分の1を軽減します。
手続きは必要ありません。
産前産後期間の軽減措置
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の産前産後の保険税が軽減します。
「出産育児一時金」の支給等により、出産の事実が確認できる場合、届出は不要です。
すでに令和6年度より適用を受けている方は、改めての届出は必要ありません。
詳細については、産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置についてをご確認ください。